
犬の予防接種には、狂犬病予防法で接種が義務付けられている「狂犬病ワクチン」と、任意で接種する「混合ワクチン」があります。どちらも飼い主さんが費用を負担するため値段は気になるところ。なかには、「室内で飼育しているし、任意なら接種しなくても…」と思う飼い主さんもいることでしょう。しかし、予防接種は愛犬に長く元気でいてもらうために欠かせないものです。今回は、犬の予防接種の種類や値段について解説します。
もくじ

犬の予防接種には、「狂犬病ワクチン」と「混合ワクチン」があります。まずは、それぞれどのようなワクチンなのかを解説します。
狂犬病ワクチンとは、狂犬病の抗体を作るために接種するワクチンのこと。狂犬病予防法により、年1回の接種が義務付けられています。
狂犬病は、致死率ほぼ100%の命にかかわる病気です。狂犬病ウイルスに感染した動物にかまれることで、犬だけでなく人も感染する可能性がある人獣共通感染症のため、予防は必須となっています。
一方、任意接種となっている混合ワクチンは、犬がかかりやすく致死率の高い病気を予防するために接種が推奨されているもの。2種・5種・8種…と複数のワクチンを1回で接種できるようになっています。
また、すべての犬に推奨されるコアワクチンと、生活環境や感染状況によって接種しておいたほうがよいとされるノンコアワクチンに分けられ、どの種類をどれくらいの頻度で接種するかは住んでいる地域や生活環境によって決められます。
【関連記事】
【獣医師監修】犬の予防接種は毎年必要?ワクチンの種類と接種の間隔を解説

犬の予防接種は、法律で義務付けられているから行うのはもちろん、予防接種をすることで愛犬が病気にかかるのを防ぎ、飼い主さんやほかの犬に病気を広げないためにも必要なものです。
ドッグランやペットホテルによっては、義務である狂犬病ワクチンはもちろん、任意の混合ワクチンも接種していなければ利用できないところもあります。
また、予防接種を受けていなくてもペット保険に加入することはできますが、予防接種を受けておらずワクチンで予防できる病気にかかった場合は補償されないのが一般的です。
ドッグランやペットホテル、トリミングサロンに通うなど、ほかの犬との交流がある場合は、狂犬病ワクチンに加えて年1回の混合ワクチン接種が望ましいでしょう。

世界小動物獣医師会(WSAVA)のガイドラインでは、生後6~8週で1回目のワクチンを接種し、生後16週を過ぎるまで2~4週に1回接種することが推奨されています。
その後、コアワクチンは3年に1回、ノンコアワクチンは1年に1回が目安といわれることもありますが、抗体のつきやすさや生活環境などによるところもあるため、一概にはいえません。
かかりつけの動物病院で相談しながら、ワクチンの接種計画を立てることをおすすめします。
狂犬病ワクチンは、生後91日以上の犬を飼い始めたら30日以内に1回目を接種します。以降、年1回の予防接種が義務となりっています。

狂犬病のワクチンは、1回3,000~4,000円ほど。混合ワクチンは、種類によって3,000円~1万円ほどが目安。
フィラリアやノミ・ダニの予防薬なども合わせると、健康であっても1歳以降の小型犬・中型犬は年間3~5万円ほど、大型犬・特大犬は4~6万円ほどの医療費がかかるでしょう。
また、犬の飼いはじめには、役所への登録料や複数回のワクチン接種など、次のような費用がかかります。
| 【犬の飼いはじめにかかる費用(目安)】 | |
| 必要項目 | 費用 |
| 登録料 | 3,000円前後 |
| 狂犬病の予防接種 | 3,000~4,000円ほど/回 |
| 混合ワクチンの予防接種 | 3,000円~1万円ほど/回 |
| 犬の飼育に必要なアイテム (ペットサークルやベッド、トイレトレーなど) |
4~5万円 |
予防接種の金額は動物病院によって異なります。早めにかかりつけの動物病院を見つけ、初期費用を確認しておくとよいでしょう。
ペット保険は病気やケガの治療の補償を対象をしているため、予防に関する医療費はペット保険の対象外となるのが一般的です。
ペット保険に加入していても、予防接種の費用は別途必要となると考えておきましょう。
予防接種の費用が補償されないのなら、ペット保険に加入しても「出費が増えるのでは?」と考える飼い主さんもいるかもしれません。
しかし、犬や猫などのペットの医療費には公的な健康保険がありません。ペット保険に加入していない場合、病気やケガの治療費も全額自己負担となります。
加入するペット保険によって自己負担額の割合は変わりますが、おおよそ5~3割の自己負担に抑えられる点がペット保険のメリットです。
軽い通院であれば、それほど家計へ負担をかけることはありませんが、通院でも検査が必要となった場合や入院・手術などが必要となった場合は、数万~数十万円の治療費が発生することもあります。
突然の支払いのためにローンを組んだり、治療を諦めたりといった選択を迫られる飼い主さんもいるため、早いうちから高額治療費が発生した場合の備えをしておくことが肝心です。

ここでは実際にあった「異物誤飲」の治療費の事例を紹介します。異物誤飲は年齢関係なく多い事故。特に0~1歳の子犬期に多いため、飼い主さんには注意してほしい傷病の一つです。
異物誤飲で7日間入院し、手術を行いました。
入院7日間、手術1回
| 治療総額 | 32万1,695円 |
ペット&ファミリー損保のペット保険、「げんきナンバーわんスリム プラン70」に加入していた場合、自己負担額例は以下の通りです。
| お支払い保険金 | 20万0,687円 |
| 自己負担額 | 12万1,008円 |
犬の治療費の高さはもちろん、ペット保険加入による飼い主さんの医療費負担が大きく軽減されていることがわかります。
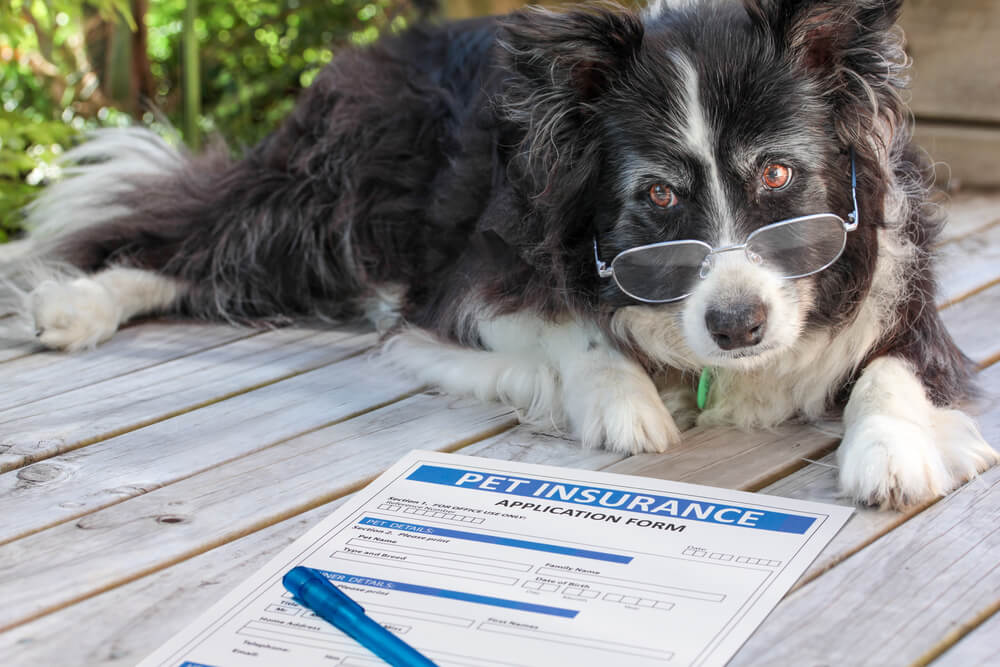
ペットの保険料は、犬の場合ペットの年齢と体重、もしくは年齢と犬種によって決まるのが一般的です。猫の場合は年齢のみで決まるのが一般的です。
ペットの年齢で保険料も変わるため、加入時の保険料だけで比較せず、ペットの平均寿命を踏まえた上で、数年単位での保険料の違いにも注目しましょう。
【1カ月あたりのおおよその保険料*1,2】
*1 慢性疾患にも、高額治療にも対応したペット保険!ペット&ファミリー損保「げんきナンバーわんスリム プラン50」
*2 犬の加入タイプ(小型犬・中型犬・大型犬・特大犬)は、ご加入時・ご継続時の体重で決まります。ただし、1歳未満の幼犬の場合「犬種分類表」を参考に、1歳時のおおよその予測体重で加入タイプが決まります。
ペット保険にはたくさんの種類があり、保険商品によって補償内容は大きく異なります。「どれも同じようだから、保険料が安いものにしよう」と判断せず、補償内容をよく理解した上で選ぶようにしましょう。
親身に対応してもらえるかなどもチェックしておくと安心です。

高額治療費の支払いに強いペット保険を選ぶならペット&ファミリー損保の『げんきナンバーわんスリム』がおすすめです。
『げんきナンバーわんスリム』の特徴は以下のとおりです。
1日に複数の検査を行うような通院、手術や入院の内容によっては、治療費が高額になるケースも少なくありません。
『げんきナンバーわんスリム』には、1日あたりの限度額がないため、通院でも最大で70万円の保険金を受け取ることができます。
年間の利用回数にも上限がないので、慢性疾患で20回を超える通院が発生しても年間の限度額内であれば何度でも保険金の請求が可能です。
ペット保険は人の保険と同様、年齢が高くなるほど保険料が高くなるのが一般的です。『げんきナンバーわんスリム』はペットの長寿化を見据えて10歳以上の保険料は一律です。
通院、入院、手術はもちろん、時間外診療費にも対応。突然の休日や夜間の診療でも安心です。
さらに、ペット保険で補償対象外となりがちな、歯科疾患※4、膝蓋骨脱臼(パテラ)、椎間板ヘルニア、先天性・遺伝性疾患、猫エイズ(猫免疫不全ウィルス(FIV)も補償対象。
先天性や遺伝性の病気が心配な、0~3歳の若齢の犬猫も安心して加入いただけます。
※1 補償期間中に受けた病気・ケガの治療に対し、保険金の年間限度額はプラン70の場合は70万円まで、プラン50の場合は50万円まで。また、1日あたり5,000円の免責金額(自己負担額)があります。
※2 保険金のお支払い対象とならない治療費がありますので、詳しくは、「補償内容ページ」「お支払い事例ページ」「重要事項説明書」等をご覧ください。
※3 今後の商品改定等により、保険料が変更となる場合があります。
※4 乳歯遺残(不正咬合を含みます)、歯列矯正などケガ・病気にあたらないもの、治療に該当しないものは保険金のお支払い対象外となります。
24D148-240718
犬の予防接種には、毎年の義務である狂犬病ワクチンと任意である混合ワクチンがあり、1 回あたりの値段は 3,000 円~1 万円となっています。
どの混合ワクチンを選ぶか、接種回数はどれくらいにするかなどはかかりつけの動物病院と相談してください。
飼い主さんの義務としてはもちろん、愛犬を守るためにも、予防接種はしっかり行いましょう。
犬の予防接種を知ろう!ワクチンの種類・費用・接種の注意点を解説
【獣医師監修】犬の予防接種の時期を知ろう!何歳から何歳まで必要なの?接種スケジュールも解説
【獣医師監修】犬の予防接種は毎年必要?ワクチンの種類と接種の間隔を解説
犬の予防接種、値段はいくら?ワクチンの種類と費用目安を解説
【獣医師監修】子犬の予防接種について解説!ワクチン接種はいつから?開始時期や注意点も紹介
【獣医師監修】予防で防げる「フィラリア」ってどんな病気?
ペットの医療費(治療費)はいくらかかる?もしもに備えるペット保険とは?
犬の予防接種を知ろう!ワクチンの種類・費用・接種の注意点を解説
子犬をお風呂に入れていい時期は?タイミングの見極め方とお風呂嫌いにしないコツ
【獣医師監修】子犬の食事、週齢・月齢別の食事内容・回数からフードの切り替えまで
【獣医師監修】子犬のお散歩はいつから?ワクチン接種が関係する?お散歩デビューのポイント解説
【獣医師監修】子犬のおやつはいつから、何をあげられる?子犬のおやつの与え方を解説
【獣医師監修】子犬の歯磨きはいつから?やり方、タイミング、頻度を解説
【獣医師監修】子犬の爪切りはいつから始める?爪切りの仕方と注意点を解説
【獣医師監修】子犬がトイレで寝るのはなぜ?理由とやめさせる方法を解説
【獣医師監修】子犬のお留守番はいつから?トレーニングや準備、お留守番の注意点を解説 (3月12日公開)
【獣医師監修】子犬がご飯を食べない!原因の見つけ方と対処法を解説
【獣医師監修】子犬が吐くのはなぜ?考えられる理由と病院受診のポイント
【獣医師監修】子犬のくしゃみの原因は?考えられる病気や対処法を獣医師が解説
【獣医師監修】子犬のしつけ方を解説!事前準備と正しいしつけ方
【ドッグトレーナー監修】子犬の鳴き声、どうしたらいい?愛犬とのコミュニケーションについて解説
【獣医師監修】子犬の甘噛み、噛み癖がつく前にやっておきたいしつけの方法
【獣医師監修】マズルコントロールはしつけに必要?知っておきたいマズルの知識
【獣医師監修】新しく犬を迎えた初日の過ごし方、迎えるために準備すること
はじめて犬を飼う人が準備すべきこと、心構え・必須アイテムを解説
【獣医師監修】ケージとクレート(キャリー)の違いは?子犬のケージの選び方
ペット保険は入るべき?「加入する・加入しない」の判断ポイントを解説
犬をお迎え(購入)する際の注意点まとめ!トラブルを防ぐために知っておきたいポイント